お臍(おへそ)が飛び出ているように見える「でべそ」は、正しくは「臍ヘルニア(さいへるにあ)」と呼ばれ、実際は「お腹の内側から腸が飛び出した状態」のことを指します。臍ヘルニアは、赤ちゃんの10人に約1人の割合で発生する疾患で、特に低出生体重児(未熟児)に多くみられます。
原因は、へその緒(臍帯:さいたい)が取れた後にへその緒が通っていた穴が塞がりきっていないことです。成長に伴い、泣く力が強くなるほど、お臍の出っ張りが目立ってきて、大きな「でべそ」となります。
臍ヘルニアとなっても、1歳児で約80%、2歳児で約90%が自然に治るため、2000年以前は経過観察となっていました。ただし、自然に治ったとしても、一度伸びてしまったお臍の周りの皮膚は「たるみ」となるため、親御さんが思われているようなお臍の形とは異なってしまうことがあります。
この美容的問題を治すには手術が必要となることから、近年は臍ヘルニアを綿球とテープなどで圧迫する治療が積極的に行われています。
ヘルニア(脱腸)が小さなうちに圧迫治療を始めることで、自然治癒と比べて早く治り、外見も良くなる傾向があるため、生後4か月頃までの治療開始が望まれます。
赤ちゃんのでべそが気になりましたら、一度お気軽にご相談ください。

臍ヘルニアとは?
臍ヘルニア(でべそ)は、腹筋が未発達な赤ちゃんにとって、誰にでも起こり得る疾患です。
ほとんどのケースで自然に治り、そのままでも危険性はありませんが、でべそが大きい程、お臍周りの皮膚がたるんでしまい、ご家族が想像しているお臍とは異なる形になってしまう場合があります。
でべそを綺麗に治すためには、小さいうちから治療することをおすすめします。
臍ヘルニアの症状
臍ヘルニアは、泣いたりいきんだりして腹圧が上がったとき、お臍の根元から腸が飛び出して、お臍が膨らんだ状態です。でべその内側は「腸」なので触ると柔らかく、指で押し込むと一時的に中に戻せます。
臍ヘルニアはへその緒が取れてくる生後2週以降に発生し、でべそと分かってくるのは、おおよそ生後1か月になる前くらいからです。
また、生後4か月ごろまでどんどん大きくなる傾向がありますが、腹筋が発達してきて寝返り・ハイハイなどができる頃には、お臍のふくらみは次第に小さくなっていきます。
臍ヘルニアの原因
へその緒が通っていた穴(臍輪)が次第に収縮していき、腹膜と癒着して穴が塞がることで「お臍」となります。
臍ヘルニアは、このお臍が完成するまでの過程で発生するものであり、泣く・いきむなどお腹の筋肉に圧力がかかると、塞がれていない穴から腸が出てしまうのです。
そのため、はじめは小さな飛び出しでも、成長に伴って腹圧が強くかかるようになると大きくなっていき、4~5cm(≒ピンポン玉)程度飛び出すことがあります。
臍ヘルニアの合併症
臍ヘルニアは、基本的には危険な病気ではありません。
しかし、まれに「ヘルニア嵌頓(へるにあかんとん)」と呼ばれる、血液障害を起こすことがあります。
ヘルニア嵌頓では、飛び出した腸が穴(ヘルニア門)に強く締め付けられ、お腹に戻らなくなります。腸液が途絶えてしまうことで、頻繁な嘔吐がみられます。ほかにも、不機嫌・腹痛・臍部の痛み・ヘルニア部分が硬くなるなどの症状が現れます。このような様子が見られたら、緊急手術が必要となりますので、すぐに医療機関を受診しましょう。
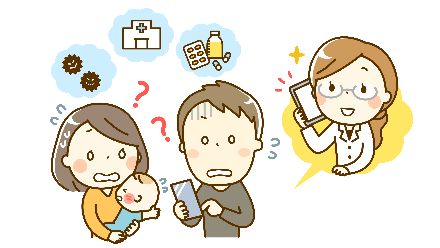
臍ヘルニアの検査・診断
泣いたりいきんだりして腹圧がかかったときに、お臍の根元から腸が飛び出たことが確認できると、「臍ヘルニア」と診断します。
おうちで飛び出たときに写真を取っておくと、診断の補助として役立ちます。
臍ヘルニアの治療
圧迫治療は、ヘルニアが小さいうちから治療を始めて、腹壁の穴が閉じるまで、継続して圧迫することが大切です。
臍ヘルニアの治療は、綿球やスポンジなどをお臍に当てて、上からお肌に優しい透明の絆創膏を貼って固定します。絆創膏は防水性なので、お風呂はそのまま入れます。
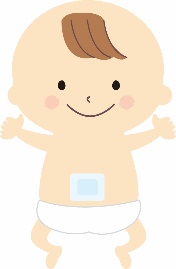
当院では、圧迫治療のやり方を一緒に確認していただいています。指導後はご家庭で圧迫治療を行っていただきます。
基本的にテープは貼りっぱなしで構いませんが、経過観察のため、月1度ご来院ください。
ただし、お肌に優しい絆創膏を使用しますが、皮膚かぶれなどトラブルが現れる場合があります。皮膚に赤みが現れたときには、すみやかにご来院ください。
なお、この圧迫治療は、絶対に行わなければならない治療ではありません。治療の継続により、ご家族や本人が負担だと思うような状況となれば、いつでも治療を中止することが可能です。将来的な外見などを含めて、よく考えてから治療をするようにしましょう。
治療についてご不明点などありましたら、お気軽にご相談ください。
圧迫治療のメリット
臍ヘルニアは自然治癒できる病気ですが、治療することで次のようなメリットがあります。
- 治療期間の短縮
自然治癒では1~2年ほどかかりますが、圧迫治療では治療開始時期が早ければ、1~2か月程度で治ります。大きいヘルニアの場合には、もう少しかかることがあります。 - 治癒率の向上
ヘルニアが小さい、つまり治療開始が早いほど早く治る傾向があります。 - 外見(お臍の形)の良さ
近年は積極的な治療が行われるようになってきたため、でべそのお子さんが珍しいことで、将来からかわれたり、コンプレックスを抱く原因となったりする可能性があります
また、結果的におへその形を整える手術を行う方は少なくありません。
圧迫治療のデメリット
- 絆創膏によって、皮膚がかぶれる場合がある
圧迫治療では、腸壁の穴が自然に閉じるまで腸が飛び出ないようにすることが目的なので、継続して圧迫、つまり絆創膏を貼り続ける必要があります。
昔と比べて、絆創膏の質が良くなり、さらに圧迫予定部分を消毒すれば皮膚炎の発生をほとんど抑えられるようになりましたが、かぶれてしまうお子さんはいます。
かぶれ具合によっては、貼る位置を変えて薬で治療しながら、圧迫療法を継続できることがありますが、酷くかぶれてしまったときには圧迫療法を一旦中断します。 - 治療開始時期が遅いと、効果がみられない場合がある
圧迫治療は、ヘルニアが小さい、つまり治療開始が早いほど効果がみられます。生後1~2か月と比べて、生後6か月以降では治療効果は低くなります。 - 臍ヘルニアの根治療法ではない
圧迫治療は自然治癒を促す治療法なので、ヘルニアが治らない、ヘルニアが治ってもお臍の形が醜くなってしまうなどのケースが起こり得ます。 必要に応じて、外科手術が可能な医療機関をご紹介させていただきます。
よくあるご質問

子どもの臍ヘルニアは、いつまで様子見していたら良いのでしょうか?
お子さんに臍ヘルニアの疑いがあるのであれば、綺麗に治すためにも、できるだけ早くご来院ください。
臍ヘルニアは2歳頃までには自然治癒することが多いので、少し前までは「2歳頃までは様子見」とされていました。しかし、2歳頃までに治らず、治療を始めようとしたときには全身麻酔による「手術」が必要となります。
一方で、近年、再び積極的に行われている「圧迫療法」は飛び出ている腸(でべそ)を綿球などで圧迫して絆創膏を貼るだけなので、お子さんの負担は少なく済みます。 圧迫治療はヘルニアが小さい生後早くに始めるほど、治療期間が短く、治癒率や外見の良さが高くなる傾向がありますので、遅くとも生後4か月までに治療を開始することが望まれます。
なお、圧迫治療は自己流で行うと、臍ヘルニアが再発したり、緊急手術が必要な合併症になったりする恐れがあるので、しっかり医師の指導の元、行う必要があります。
臍ヘルニアの手術では、どんなことを行いますか?
2歳頃まで経過観察をしていた、圧迫療法をしたが治らなかった、お臍が醜い形で治ってしまったなどのケースでは、1歳半~2歳頃にお臍の形を整える手術を行います。
全身麻酔をして、お臍に沿って切開し、閉じていない臍輪を縫合します。手術時間は1時間程度で、1泊2日または日帰り手術で行えます。
圧迫治療を行っていた場合には、お臍周りの皮膚の伸びが少なく、小さな傷で手術が行えるので、傷跡はほとんど目立ちません。
まとめ

「でべそ(臍ヘルニア)」は、赤ちゃんのときに誰でも起こりやすい病気ですが、見た目から将来を心配される親御さんは、少なくありません。
また、「でべそ」という別名から、お臍が飛び出ているイメージがあるかもしれませんが、正しくは腸が飛び出ている状態です。でべそを放置していても自然と治ることがほとんどなので、昔は「自然治癒する2歳頃まで様子見」とされていました。 しかし、でべそが治っても、お臍周りの皮膚のたるみが残るケースがあり、きれいなお臍にするには手術が必要となります。
近年は手術を避け、お臍をきれいに治すために積極的な「圧迫治療」が行われています。治療開始が早ければ早い程、治療期間が短く済み、治療効果が高く、見た目が良い傾向があるため、遅くとも生後4か月までには治療を始めたいです。
赤ちゃんのお臍で気になることがありましたら、一度ご来院ください。

